はんだ付け講習・検定 @滋賀の協会セミナールーム レポート
皆様こんにちは!
本日も昨日に引き続いて滋賀県の協会セミナールームにて
はんだ付け講習・検定を開催しています。

本日の午前中は微細はんだ付け(100ピンQFPや1005・1608チップ)を行う
1級の方の講習を行っております。
今回、受講者様とお話をしている中でこのようなお話がありました。
「B型(エンピツ型)のコテ先しか使ったことが無かったので、今回C型やD形のコテ先を使って、
コテ先を選定してはんだ付けすれば作業性や品質が大きく変わるのが分かりました」
「プリント配線パターンの違いで熱の伝わり方が違ってくるということがよく理解できました」
はんだ付け講習・検定では、コテ先を複数用意させて頂いており、はんだ付け対象物に応じて最適なコテ先に交換しながらはんだ付けを行っていきます。
また、はんだ付けを行う教材は、様々な配線パターンを用意しておりそれらの形状で熱の伝わり方が変わるように設計しています。
その為、ランドの形状に応じて効率的に熱を伝えやすい形のコテ先を選定する、熱が逃げそうな場所には太目の熱容量が大きなコテ先を選定する、などといった事を効率的に習得することが出来ます。
先のお声を聴いて、普段“当たり前”と思って使っている道具や基板の条件が、実際には大きく作業性や仕上がりに影響を与えることを、講習を通じて理解していただけたと感じました。

受講者アンケートで次のようなお声を頂きましたのでご紹介いたします。
🎤仕事でたまにはんだを使うことがありますが、教えてもらったことは無かったので、
細かく教えて頂き、はんだの事も理解することが出来ました。
🎤設備がとても大切なことを強く感じた。
🎤解説が分かり易かった。3人の講師さんでわからない事も聞き易かった。
自己流では気づきにくいはんだ付けの基本や、コテ先の選定の重要性などをはじめ、たくさんの事を本講習で学び、習得頂けたことと思います。
また、講師陣との距離が近いことも本講習の特徴で、安心して質問が出来る雰囲気もございます。
はんだ付け講習を通じて、「ただ融かしてつける」から一歩進んで、なぜこの道具を選ぶのか・なぜこの条件ではんだ付けをするのか、という視点を学んでいただけたと確信致しました。
ありがとうございます。
今後のはんだ付け講習・検定の予定は
以下のカレンダーから確認することが出来ます。
講習・検定カレンダー
それでは皆様、明るいはんだ付けを!





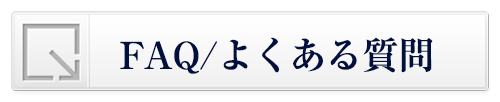



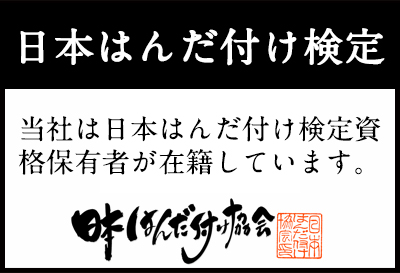 はんだ付け検定 認定者在籍マークは、はんだ付け検定合格者が在籍しており、はんだ付け作業に従事していることを当協会が認定したことを示すマークです。
はんだ付け検定 認定者在籍マークは、はんだ付け検定合格者が在籍しており、はんだ付け作業に従事していることを当協会が認定したことを示すマークです。