はんだ付けに光を!(その素材、はんだ付けしても大丈夫?)
こんにちは、はんだ付け職人です。
企業様へ訪問して行うカスタム講習で気づいた点の第3弾です。
③はんだ付けされる素材が悪い場合
そもそも、はんだ付けの対象物がはんだ付けに向いていないというケースもよくあります。
リード線の中には、②の予備はんだが弾いてしまって、馴染まない素材のものが存在します。
ポリウレタン銅線などは、被膜が強固で420℃程度無いと融かすことが出来ませんが、
ハンダゴテのコテ先温度は、通常そんな高温まで上げませんので、
専用のワイヤーストリッパを使用したり、予備はんだに高温設定したはんだポットや
専用ハンダゴテを用意したりします。
また金属の素材では、例えば亜鉛(Zn)を含む金属(例えば真鍮など)は
そのままでは、はんだ付けには適さず、はんだ付け後にいろいろな不具合を引き起こすため、
充分なメッキが必要である・・ことなどはあまり知られていません。
(普通にはんだ付けできるので見逃しがち)
他の例では金は、安定した金属ではんだの濡れ、馴染みも抜群に良い素材ですが、
金メッキが厚くて、はんだに溶け込む量が3重量%を超えると危険域とされています。
(接合部にAuSn₄が多量に析出し、クラック(ひび割れ)が発生しやすくなる)
こうした課題は、10~40年前は、古い職人さんや技術者が知っていたことですが、
最近では、ほとんどのはんだ付けが自動化されてきたため、
こうした知識が若い世代に引き継がれなくなってきたために出てきています。
はんだ付けはAIが活躍し始めた現在でも、エレクトロニクスには必須の根幹技術です。
ともすれば軽視されがちですが、今でも電気製品の不具合の大半は「はんだ付け」が原因です。
一度「はんだ付けに光を!」当ててみてはいかがでしょう?
お役に立てば幸いです。
明るいはんだ付けを!





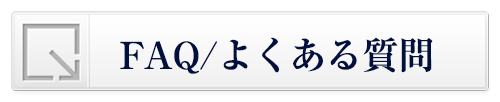



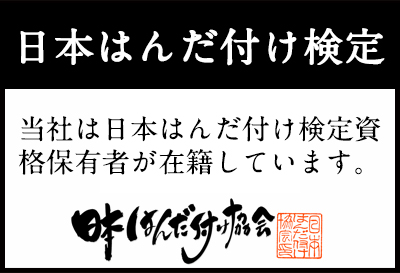 はんだ付け検定 認定者在籍マークは、はんだ付け検定合格者が在籍しており、はんだ付け作業に従事していることを当協会が認定したことを示すマークです。
はんだ付け検定 認定者在籍マークは、はんだ付け検定合格者が在籍しており、はんだ付け作業に従事していることを当協会が認定したことを示すマークです。