はんだ付けに光を!(予備はんだは、ムッチャ重要)
こんにちは、はんだ付け職人です。
企業様へ訪問して行うカスタム講習で気づいた点の第2弾です。
②リード線、ケーブルに予備はんだをしていない。
予備はんだをしている目的が理解できていない

(※良い仕上がりの予備はんだ)
これは意外なんですが、予備はんだの重要性が理解されていないケースが多いです。
あるいは予備はんだをしていても、何が目的で予備はんだを行ってるのか理解しないで
形だけやっているため、逆効果になっているケースもあります。
リード線、ケーブルに予備はんだをしなくてもOKな条件は少ないです。
リード線、ケーブルがはんだ付け対象物に比較して熱容量的に十分に小さくて
酸化などの恐れがない場合に限られます。
リード線に予備はんだがされていない場合、はんだ付けは非常に高難易度のものとなり、
コネクタや端子にリード線をはんだ付けしても、
リード線にはんだが馴染んでいない不良が発生する。
あるいは、無理に馴染ませようとして、オーバーヒートを起こして、
はんだ量が過多になってしまう場合が多いです。
中には、「工数を増やしたくない」とおっしゃる方もいらっしゃいますが、
自社商品の仕掛品の中から抜き取りで実体顕微鏡で検査した結果、
不具合品を多数検出して、
「この製品いつから出荷してる?!」
「こんなにひどいのか・・」
「たまたま大丈夫やっただけで、怖いなあ・・」
と認識を改めていただけます。
また、予備はんだ済みのケーブルを外注から入手して、そのまま使用されている場合、
一度、その予備はんだの仕上がり状態を実体顕微鏡で観察してみると、
高確率で予備はんだが不十分なモノが見つかります。

(※失敗した予備はんだ 肉眼で見つけることは難しい)
リード線の予備はんだには、はんだをリードに浸透させて馴染ませる時間が必要ですが、
数と効率を追ってしまうと、十分に馴染ませる時間が取れずに不完全な状態で
予備はんだされたリードが混入するわけです。
一度、自社の予備はんだが大丈夫かどうか点検してみてはいかがでしょうか?
お役に立てば幸いです。
明るいはんだ付けを!





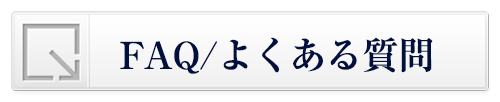



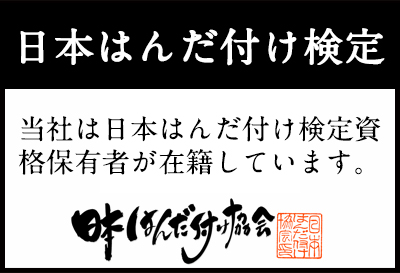 はんだ付け検定 認定者在籍マークは、はんだ付け検定合格者が在籍しており、はんだ付け作業に従事していることを当協会が認定したことを示すマークです。
はんだ付け検定 認定者在籍マークは、はんだ付け検定合格者が在籍しており、はんだ付け作業に従事していることを当協会が認定したことを示すマークです。