株式会社エクセディ様で はんだ付け講習会を開催
皆様こんにちは。
9/5に株式会社エクセディ様にお伺いして、6回目となる
はんだ付け出張講習を開催させて頂きました。
今回の受講者は13名様、外国人の方も2名受講されております。

エクセディ様では、マニュアルクラッチやトルクコンバータなどの自動車や二輪車の駆動系部品の生産を行っており、昨今、このトルクコンバータで培った技術を応用して、ドローンプロダクトも手掛けてらっしゃいます。
今回は、主に開発グループの方が受講されております。

実習内容としては、ドローンではモーターなどの大きな電流が流れるコネクタが存在するため、
それらに合わせてカスタムさせて頂いた内容をご用意させて頂いております。
プリント基板へのはんだ付けでは、3216サイズチップ部品の表面実装はんだ付けや
アキシャル部品のスルーホールへのはんだ付けなどを行っていただきました。
コネクタピンの太さや、基板の配線パターンの違いによって
熱の伝わり方が大きく変わってくるため、特に大きな熱量を必要とするパターンでは
部品の端子ではなく基板面からしっかりと熱を伝えることが大切になります。
(なかなか融けないので焦って無理やり糸はんだを送り込んだ結果イモはんだ(熱不足)になる、というパターンをよくお見受けするように感じます・・・)
このような作業のポイントを、あらかじめ eラーニングで学び、そして、ご自身で実際にやってみる。
また、講師の実演から学びご自身の作業へフィードバックして頂けました。
(実演してご説明させて頂いた時に「すごくわかりやすいです!」と言って頂けて、思わずニヤけてしまったのは内緒です)

最後の質疑応答の時間には、積極的に質問いただきました。
開発案件で公に出来ない内容もありますが、
「はんだ付け部にクラックが入ることがあると聞きましたが、
どういった原因で起こるのでしょうか?」
といういい質問が出ました。
①はんだ付け部に応力が掛かるような設計、構造になっていると、はんだ付けは必ず
時間を掛けて破壊される
②例として、家電品のUSBの充電コネクタは、充電のたびに応力が掛かるため、
最も壊れやすい部位である。何度も応力が掛かるようなところに使用するコネクタは、
ネジ留めするなどの対策が必要。
③別の例として、電解コンデンサなどの背の高い部品は、自動車の振動で大きなモーメントが
働くのではんだ付け部が壊れやすい。振動対策に樹脂などで固定するなどの手法がとられる。
といった回答をさせていただきました。
アンケートでいただいた受講者の声を一部紹介させていただきます
・はんだの良品不良品の判断基準が理解できた
・今まで何となく作業していたはんだ付けには明確な手順と方法があったということ
・はんだする際ははんだごての適切な温度設定が重要であること
・半田にもクラックの概念が存在したのを知った
・はんだの基礎が判り、これまでのやり方で間違った点に気づくことができた
・受講してなかったらずっと誤ったはんだ付けを行っていた事になるので、参加してよかった
・実習を通じることでより業務に生かしやすく、今後の実務に繋げていけると感じた
・自己流でやることが多いはんだ付けの基礎を学ぶことで、
確実で綺麗なはんだ付けをするスキルが得られた
・事前にe-ラーニングの座学講座があったので、そこで得た内容を意識しながら、
実技が受講でき、より理解につながった。
なかなか熟練レベルの方のやり方を間近に見る機会がないので、とても有益だった
・センサー取付時にはんだを使用することがあるため、講義で学んだことを生かして
適切なはんだとりつけを行いたい
・様々な部品に対して、はんだ付けの実習を行うことで、作業として共通している項目、
特別に考慮しなければならないことを理解することが出来た。
1日間の実習であったため、時間が限られていたが、知識・技術共に
向上することが出来た講習でした。ありがとうございました。
・はんだ付けは、自己流でされる方が多いし、私も自己流で今までやってきた。
この講習でその基礎を学ぶことで、少しポイントを知っているだけで
キレイで確実なはんだ付けが出来き、今後の業務や個人の趣味にも役立つスキルを
得ることが出来た。ありがとうございました。
・はんだの基礎を知ることが出来、これまでの間違ったやり方に気づけた。
また、良品を知ることが出来た。
・I was able to lean and practise tha correct we of Soldering.
・どうすれば品質、見た目ともに良いはんだ付けが出来るかが
理屈をもとに理解でき、とても有益でした。
・今まで独学でやっていたことを改めて正しく学ぶことで
今後の業務に活かすことが出来ると感じました。
エクセディ受講者の皆さん ありがとうございました。
出張講習のカスタム
出張講習は、企業様の仕事内容に合わせてカスタムが可能です。
「うちは、コネクタしかはんだ付けしない」
「うちでは、基板実装ばかりで、特に表面実装がほとんどだ」
「うちでは、基板同士を接続するのが主だ」
といった仕事内容に合わせて、理解しやすいように
豊富な教材の中から実習の内容を組み合わせてカスタムして提案いたします。
ご相談はこちらから。

皆様からのご連絡を、お待ちしております。





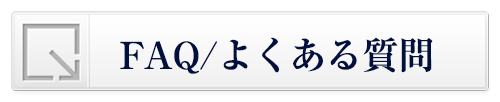



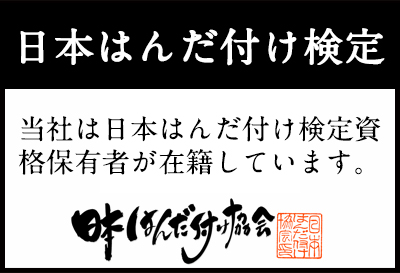 はんだ付け検定 認定者在籍マークは、はんだ付け検定合格者が在籍しており、はんだ付け作業に従事していることを当協会が認定したことを示すマークです。
はんだ付け検定 認定者在籍マークは、はんだ付け検定合格者が在籍しており、はんだ付け作業に従事していることを当協会が認定したことを示すマークです。